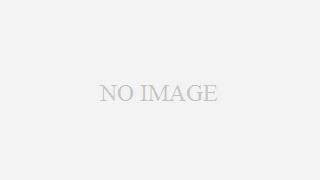 睡眠
睡眠 病院で処方される 睡眠薬 の種類と作用について
医師が処方するメジャーな睡眠薬について、どれくらい知っていますか?睡眠の悩み、と聞いて、「睡眠薬」を連想するかたも多いはずです。規則正しい生活や食事だけではなかなか不眠が改善せず、「とにかく眠れない」「眠りたい」というとき、睡眠薬は助けにな...
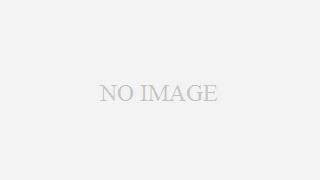 睡眠
睡眠 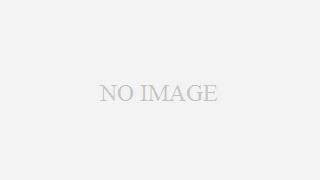 睡眠
睡眠 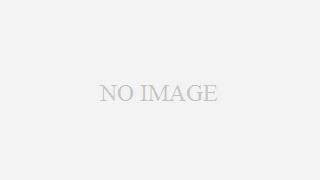 睡眠
睡眠