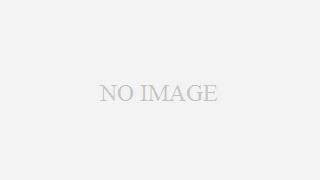 健康は良質な睡眠から
健康は良質な睡眠から 目覚めをさわやかにする眠り方
目覚めのよい睡眠サイクルを知るひどい睡眠障害を起こすと、免疫機能(体の防御機構) も低下するので、さまざまな病気にもかかりやすくなります。私たちが健康で満足できる生活を送るためには、健康な睡眠の確保が必要というわけです。睡眠には、ノンレム睡...
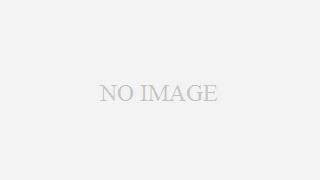 健康は良質な睡眠から
健康は良質な睡眠から 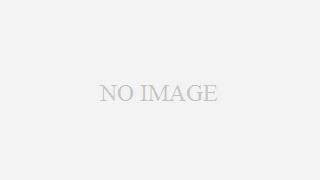 健康は良質な睡眠から
健康は良質な睡眠から 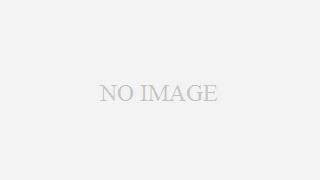 健康は良質な睡眠から
健康は良質な睡眠から