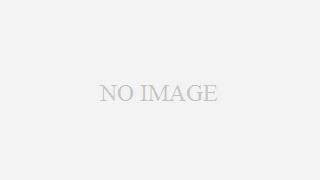 快眠食
快眠食 メラトニン健康食品の上手な活用法
体内のリズムを調整し睡眠障害を改善「メラトニン」は、脳の奥深くにある松果体という器官から分泌される脳内ホルモンの1つです。1997年、アメリカでこのメラトニンが「万病に効く奇跡のホルモン」とマスコミに取り上げられ、大センセーションを巻き起こ...
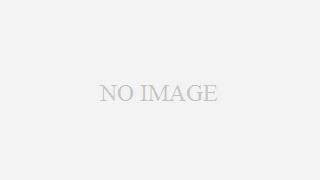 快眠食
快眠食 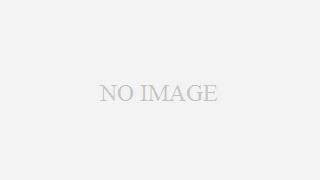 快眠食
快眠食 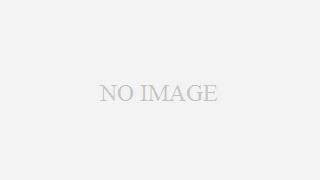 快眠食
快眠食