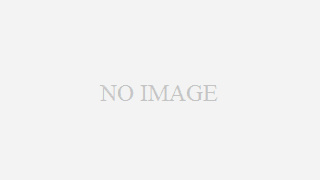 眠るまでの過ごし方
眠るまでの過ごし方 眠るまでの過ごし方(一覧)
毎日の大切な睡眠ですが、自分の眠りに満足している人って、どれくらいいるでしょうか?寝つくのに時間がかかる途中で目が覚める深く眠れない眠っても疲れがとれないなど、睡眠についての不満はいろいろあるでしょう。よく眠れない人は眠れないことで悩んでい...
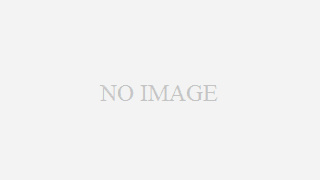 眠るまでの過ごし方
眠るまでの過ごし方  眠るまでの過ごし方
眠るまでの過ごし方 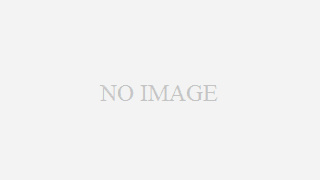 眠るまでの過ごし方
眠るまでの過ごし方