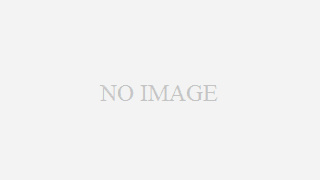 睡眠をもっと知ろう
睡眠をもっと知ろう 夢のメカニズムと眠る姿勢
皆さんは自分が見た夢を覚えているでしょうか?夢は、ほ乳類のほとんどが見るといわれていて、眠っている間の頭の中では現実とは異なった不思議な世界がひろがっています。基本的に、夢はレム睡眠(浅い眠り)の時に見ることが多いといわれていますが、脳はそ...
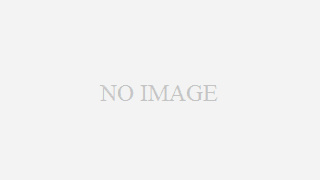 睡眠をもっと知ろう
睡眠をもっと知ろう 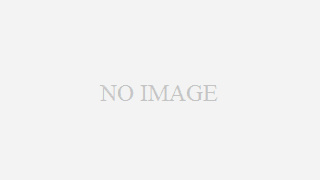 睡眠をもっと知ろう
睡眠をもっと知ろう 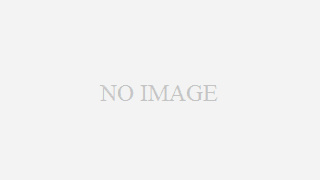 睡眠をもっと知ろう
睡眠をもっと知ろう